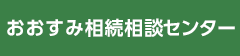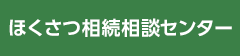土地の生前贈与と相続、どちらがお得?
税金・手続き・将来のリスクまで徹底比較!
親から子へ不動産(土地や建物)を引き継ぐ際、「生前贈与」と「相続」のどちらを選ぶべきか。これは、多くのご家庭で直面する重要なテーマです。特に土地のような高額資産を引き継ぐ場合、税金や手続きの違いによって数百万円単位の差が生じることもあるため、慎重な判断が求められます。
相続財産には不動産のほか、預金や現金、株式などさまざまな資産が含まれます。たとえば、300万円の預金でも、他の財産と合算されることで相続税の課税対象となる可能性があるため、資産全体を把握することが重要です。
実際、「相続の方が税金が安い」と聞いたことがある一方で、「トラブル防止のため生前贈与を検討したい」と考える方も多く、どちらが“得”かは一概には言えません。
本コラムでは、生前贈与と相続について、税制や手続き、節税の可能性、リスクなどを総合的に比較し、あなたに合った選択をサポートします。制度の違いだけでなく、家族構成・将来設計・介護や事業承継の観点からも具体的な判断材料を紹介します。
生前贈与と相続の基本的な違い
生前贈与とは?
生前贈与は、本人が生きているうちに配偶者や子、孫などに財産を移転する制度です。
適切な時期を見極めて活用することで、「贈与税の負担」や「相続財産の精算」も視野に入れた計画的な対策が可能となります。例えば、親が高齢となり「元気なうちに資産整理をしたい」というニーズに応える形で利用されることが多く、贈与税が発生しますが、各種特例を活用することで税負担を抑えることも可能です。
主なメリット:
- 受贈者のタイミングに合わせて資産を渡せる
- 成年後見制度を回避できる可能性
- 早期に資産活用(賃貸経営等)できる
相続とは?
相続は、被相続人の死後に、法定相続人が財産を承継する制度です。亡くなった方の資産全体を分割し、相続税の対象となる場合がありますが、多くの優遇措置があるため、計画的に行えば節税効果が期待できます。
また、相続では、遺言の有無が手続きの複雑さを大きく左右します。仮に遺言がなければ、法定相続人全員との遺産分割協議が必要になり、遺留分を主張する相手との交渉も発生するケースがあります。
主なメリット:
- 相続税の基礎控除や各種特例が充実
- 登録免許税や取得税が贈与より軽減される
- 配偶者は大幅な相続税控除を受けられる
制度と税金の徹底比較
相続の際は、「相続税の基礎控除」の計算を行い、課税対象となる財産の総額を正確に把握する必要があります。特に「土地」や「建物」といった不動産は評価額が高くなりがちであり、控除の対象や金額によって相続と贈与の税額は大きく変わります。
こうした場合には、制度の比較と共に、家族の状況に応じた選択が求められます。
| 比較項目 | 生前贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 税金 | 贈与税(特例あり) | 相続税(基礎控除あり) |
| 不動産取得税 | 原則課税 | 非課税(一定条件下) |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の2% | 同0.4% |
| 手続きの手間 | 比較的簡単(贈与者と受贈者) | 複雑になりやすい(遺産分割や相続人多数) |
| 特例 | 相続時精算課税、配偶者控除 | 小規模宅地特例、配偶者控除など多数 |
【実例で見る】税金シミュレーション
たとえば、土地の評価額が2,000万円だった場合の比較は以下の通りです。
- 生前贈与
登録免許税:約40万円
不動産取得税:約60万円(軽減前)
贈与税:課税対象(特例を使えば非課税も可能) - 相続
登録免許税:約8万円
不動産取得税:非課税
相続税:基礎控除以下なら非課税の可能性
ここからもわかる通り、金銭的負担は相続のほうが軽くなることが多い一方、生前贈与はタイミングの柔軟性や対人トラブルの回避など別の価値を提供します。
手続き面から見た違いと注意点
- 生前贈与:贈与者と受贈者の2者で完結。比較的スムーズ。
- 相続:戸籍収集、遺産分割協議、相続登記などが必要。兄弟姉妹間での争いに発展するケースも多数。
生前贈与が向いているケース
- 子どもに早く不動産を譲って管理を任せたい
- 将来、認知症発症の可能性があり、判断能力が不安
- 相続人同士で争う可能性が高い
- 介護資金や老後資金の確保を目的とした売却が視野にある
相続が向いているケース
- 贈与税を回避したい(特に高額物件の場合)
- 配偶者控除や小規模宅地の特例を使って節税したい
- 遺言などで計画的に相続分をコントロールできている
よくある失敗とその対策
- 専門家に相談せず、贈与税を想定以上に負担
- 成年後見制度が必要になり、名義変更がストップ
- 共有名義になって売却や活用が不可能に
どのような方法を取るにしても、事前相談の有無で大きな差が生じます。「贈与したつもりが、申告を忘れてお金の出所が特定できずに税務署から指摘を受けた」というケースも少なくありません。現金や預金での贈与であっても、必ず記録と申告をセットで行うことが大切です。
生前からできる節税対策まとめ
- 暦年贈与の活用(年110万円)
- 相続時精算課税制度で2,500万円まで贈与非課税
- 配偶者控除で2,000万円の住宅資金贈与非課税
- 評価額の低いタイミングで不動産を贈与 or 売却
不動産は評価額の増減が大きいため、相場と税制改正を見極めたタイミング戦略が重要です。生前贈与を選択する場合には、贈与税の税率や控除額に注意が必要ですが、タイミングを見計らった活用により、結果的に相続より得になるケースもあります。
祖父母が孫に教育資金を渡す場合でも、使い方によっては贈与税の課税対象になることがあります。生前贈与では、10万円ずつ複数年にわたって贈与する方法も活用されています。特に、将来的に1億円を超える資産を相続する可能性があるご家庭では、早めに節税対策の予約的な実行を考えることが有効です。
ただし、非課税制度を利用するには、金融機関経由での手続きや贈与の申告が必要となるため、事前確認が重要です。
2024年以降の贈与・相続税制改正に注意!
近年、国税庁や財務省の方針により、相続税・贈与税の一体化(資産移転の公平化)が進められています。特に2024年以降の改正では、「相続時精算課税制度」と「暦年贈与制度」の見直しが大きなポイントとなりました。
改正ポイント①:相続時精算課税制度の利便性向上【2024年施行】
これまでの課題:
相続時精算課税制度は「2,500万円まで贈与税が非課税になる」一方で、その後の相続時に全額が相続財産に加算されるため、一度選ぶと変更できない使いにくさがありました。
2024年からの変更点:
- 新たに“年間110万円の非課税枠”が追加されました。
→ 従来の制度に比べ、少額贈与と組み合わせて柔軟な資産移転が可能に。 - 登録手続きも簡素化が進み、制度の活用ハードルが下がったのが大きな変化です。
今後、相続時精算課税制度はより実用的な選択肢に変わりました。
改正ポイント②:暦年贈与の「持ち戻し期間」延長【2027年施行予定】
これまでの制度:
- 相続開始前「3年以内の贈与」は相続財産に含まれ、相続税の課税対象になっていました(いわゆる持ち戻し規定)。
2027年からの改正内容:
- この期間が「7年以内」に延長されることが決定。
- つまり、亡くなる7年前までに贈与された財産も相続税の計算に含めることになります(※110万円以下の贈与は除外)。
これにより、“早めの贈与”の意義がより大きくなります。
たとえば、60代・70代のうちに計画的な贈与を進めておくことが、税負担を抑えるためのカギとなります。
注意したいのは「制度が複雑になった」という点
2024年以降の税制は、一見すると選択肢が増えて良さそうに見えますが、実際には「いつ・どの制度を選ぶか」で最終的な税額が大きく変わるという複雑な状況になっています。
そのため、下記のようなタイミングでは、専門家に相談しながら制度の選択を進めることを強くおすすめします。
- 贈与を数年に分けて行いたいと考えている
- 相続時精算課税制度を使うか迷っている
- 将来の相続税をできるだけ抑えたい
専門家と連携して最新制度に対応を!
相続や贈与では、制度の正しい活用によって数十万円〜百万円単位の節税が可能になります。必要な手続きや費用の総額を見積もるには、実際の資産内容に合わせたシミュレーションが不可欠です。
南九州相続相談センターでは、ご家庭ごとの資産・家族構成・将来計画に応じて、どの制度を活用すべきかを一緒に考え、無駄な税金を払わないためのサポートを行っています。
▶ 相談申込はこちら
続けて、法人の場合についても触れておきましょう。
法人名義の不動産贈与はできる?その実務と注意点
個人の生前贈与と異なり、法人が保有する不動産を役員や家族に贈与する場合は、より高度な税務と法務の判断が求められます。
法人→個人の「贈与」は実は非常にハードルが高い
たとえば、法人が長年保有している事業用地や収益物件(アパート、駐車場など)を、経営者のご家族に「贈与」したいと考えるケースがあります。
しかし、実務上は下記のような税務上の問題が生じます:
- 法人側に「寄附金」として損金不算入となる可能性
- 受贈者(個人)には時価での「所得税」課税
- 不動産取得税や登録免許税の課税も個人贈与と同様に発生
つまり、単純な「贈与」形式はほとんどのケースで税務的に不利であり、あまり現実的ではありません。
代替案:「不動産信託」や「譲渡」を活用した承継
代わりに近年増えているのが、次のような方法です。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| ① 法人が保有しつづけ、役員家族を受益者とする信託を設定 | 所有権は法人のまま、家族に賃料収入が入るように設定可能 |
| ② 収益物件を時価で譲渡し、資金調達や節税を組み合わせる | 法人・個人間の売買として処理。資金や借入の検討が必要 |
| ③ 法人解散に向けた清算・分配 | 資産処分後の残余財産分配で対応。事前計画が重要 |
収益物件 × 家族信託 の活用でできること
収益物件(アパート、賃貸マンション、店舗物件など)を持つご家庭では、家族信託を活用することで「所有者」と「管理者・収益受取者」を分けるという新しい資産管理の仕組みが使えます。
《具体事例》
鹿児島市の60代男性(自営業)からの相談:
「老後に備えて、賃貸アパートの運営は息子に任せたい。でも名義をすぐに移すと贈与税がかかるし、まだ自分で売却判断はしたい。」
このケースでは、以下のように信託契約を活用しました:
- 賃貸アパートを父(委託者・受益者)のまま、信託設定
- 息子を受託者に指定し、運営や入居者対応を任せる
- 売却の意思決定や家賃収入は引き続き父がコントロール
- 信託契約書には、将来の相続時に自動的に所有権が息子に移る条項も記載
このスキームのメリット
- 名義変更による贈与税なし
- 高齢化・認知症リスクへの備えとして機能
- 万が一の際にも、信託契約の内容に基づいて資産移転が可能
専門的な信託設計と法人顧問対応が重要
法人名義の不動産や収益物件については、税理士・司法書士・行政書士が連携して対応する必要があります。特に、以下のような方は専門的な支援が必須です:
- 賃貸経営を法人化している方
- 将来的に事業承継や法人解散を検討している方
- 高齢のオーナーが複数の物件を保有しているご家庭
南九州相続相談センターでは、こうした法人・信託対応も可能な司法書士・税理士ネットワークを活かし、法的・税務的に安全なスキーム設計を行っています。
よくあるご質問とリアルなケースから学ぶ
相続や贈与のご相談では、お客様から次のような質問が寄せられます。
- 「200万円くらいの土地の評価でも贈与税は発生しますか?」
- 「贈与を受けたら名義変更にどのくらいの総額がかかるのでしょうか?」
- 「信託ってよく聞くけど、どんな場合に使うんですか?」
- 「祖父母が孫に財産を残したいと言っているけど、何か特別な制度はありますか?」
これらの質問の背景には、手続きの不安や、制度の複雑さ、費用の見通しの立てづらさなどが隠れています。特に最近では、「将来家族に迷惑をかけたくない」という理由から、生前贈与や信託契約のニーズが急増しています。
【事例】祖父母から孫への贈与相談
《ケース紹介》
宮崎市にお住まいの70代の祖父母から、「大学進学予定の孫に、教育費として200万円を贈与したい」というご相談がありました。
ポイント解説:
- 単純に200万円を振り込むと贈与税の対象になる可能性があるため、「教育資金一括贈与の特例(非課税)」のご案内を行いました。
- また、将来の認知症リスクをふまえ、資産全体を管理する方法として「家族信託契約」のご提案も実施。
- 手続きにかかる費用の総額や必要書類を一覧にして丁寧に案内し、「信託の内容」や「手続きの流れ」も分かりやすくご説明しました。
請求や契約に関するトラブルを防ぐには?
相続や贈与の手続きでは、不動産登記費用の請求金額や、税理士・司法書士との契約内容があいまいなまま進んでしまうと、後から「こんなにかかるとは思わなかった」というトラブルに発展することもあります。
そのため、南九州相続相談センターでは、
- 手続きごとの費用の目安(登録免許税、登記手数料、贈与税)を総額でご提示
- 各種サービスの契約内容を文書で明示
- 後から追加で請求が発生しないよう、事前に必要項目をすべて案内
といった丁寧な対応を徹底しています。
専門家による無料相談で、今すぐ「不安」を「安心」に変える
「まだ相続は先の話」と思っていても、突然の出来事で急に相続手続きをしなければならなくなるご家庭も少なくありません。
今のうちに、制度の内容や手続きの流れを把握し、ご家族にとって最も納得のいく形を見つけておくことが、将来のトラブルを防ぐ第一歩です。
相続や贈与は、「どこまでを財産として扱うか」「誰に、どの範囲まで贈与するか」など、多くの要素を考慮したうえで計画する必要があります。家族構成や資産の種類によっては、遺言や遺留分など、より高度な知識が求められる場面もあります。
以下に専門家に相談すべきタイミングについてまとめを案内します。
- 相続登記や贈与登記の準備を始めたとき
- 不動産や金融資産の規模が大きいとき
- 家族構成が複雑(前妻の子どもなど)
- 相続税や贈与税の節税をしっかりしたいとき
南九州相続相談センターでは、相続や贈与に強い司法書士・税理士が無料でご相談を承ります。
ぜひ、事前の準備・判断材料としてお気軽にご相談ください。
▶ ご相談はこちらから:相談申込