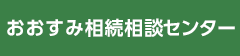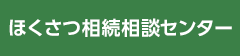公民館講座「はじめての相続・登記の授業」を開催しました
「はじめての相続・登記の授業」を開催
2025年3月24日、西田文化協会2階にて、公民館講座「はじめての相続・登記の授業」を開催いたしました。
ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
この講座は、「相続や登記について基本から学んでみたい」「いざという時に慌てないよう、正しい知識を身につけておきたい」という方を対象に、相続の仕組みや手続き、登記の重要性などを、初心者にもわかりやすく解説する内容で実施しました。

法定相続と遺産分割協議について
まずは、相続の基本として法定相続のルールや順位、相続人の範囲についてお話ししました。
「配偶者と子ども」「配偶者と親」「配偶者と兄弟姉妹」など、家族構成によって異なる相続分を具体例を交えてご紹介し、その後、遺産分割協議によって法定相続分とは異なる遺産の分け方が可能になること、それには相続人全員の合意が必要であることなど、実務的な視点からもお話ししました。
遺留分とは?
相続人間でのトラブル回避にも関わる遺留分についてもご説明しました。たとえば、「すべての財産を特定の子だけに相続させる」という遺言書があっても、他の相続人(例えば、他の子や配偶者)には最低限の権利=遺留分が保障されていることを紹介しました。遺言を書く際も、この制度を知っておくことがトラブル防止につながるという点を強調しました。
相続放棄と未成年者の対応
また、相続放棄についても詳しく触れました。
「相続したくない」「借金が多い」「自分には関係ないと思っていた」などの理由で相続を放棄する場合は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
特にご質問が多かったのは、子どもが未成年である場合の相続放棄についてです。この場合、親権者が代理で手続きを行う必要があり、また兄弟が複数いる場合は、利益相反となるため特別代理人の選任が必要になるケースもあることをご説明しました。
生前贈与と相続税、相続時精算課税制度
次に、生前対策のひとつとして関心の高い生前贈与と相続税についても解説しました。
暦年課税による年間110万円の非課税枠のほかに、相続時精算課税制度の活用についても触れ、「この制度を使うと贈与額が2,500万円(今後3,000万円に拡充予定)まで非課税で贈与できるが、最終的には相続財産に合算される」「一度選択すると暦年課税には戻せない」など、制度のメリット・デメリットも含めてお話ししました。
また、相続税の申告は原則10か月以内、納税資金の準備は計画的に進めておくことの大切さについてもご紹介しました。
相続登記の義務化と流れ、国庫帰属制度について
続いて、2024年4月から施行された相続登記の申請義務化について解説しました。
これまで放置されがちだった不動産の名義変更ですが、今後は相続開始を知ってから3年以内に登記申請が義務となり、怠った場合には過料(最大10万円)が科される可能性があることをご説明しました。
あわせて、実際に不動産の相続登記を行う際の基本的な流れについてもお伝えしました。
相続登記の一般的な流れ:
被相続人の戸籍を取得し、相続関係を確認
遺言書があればその検認または公正証書の確認
遺産分割協議書を作成(協議が必要な場合)
登記申請書の作成と必要書類の準備
法務局への登記申請(不動産所在地を管轄する法務局)
登記完了後、登記識別情報等の取得
こうした手続きは、相続人が複数いる場合や書類の取得に時間がかかることもあり、早めの準備が大切であることを強調しました。
さらに、相続したくない土地を手放す選択肢として、2023年に創設された相続土地国庫帰属制度についてもご紹介し、利用できるケースや申請の条件、実際にかかる審査・負担金についても簡単に触れました。
成年後見制度について
将来、認知症などで判断能力が不十分になったときに備える制度として、成年後見制度についてもお話ししました。
ご本人が元気なうちに後見人を指定できる任意後見と、家庭裁判所が選任する法定後見の違い、それぞれのメリット・注意点を実際の事例をまじえて解説し、参加者の皆さまも大変関心を寄せておられました。
講座を終えて
講師が熱意を込めてお話しした結果、当初予定していた時間を大幅に超える講座となりましたが、皆さま最後まで熱心にご参加くださり、終了後も個別のご質問が相次ぐなど、充実した内容となりました。
参加者からは
「ここまで幅広く説明してくれると思わなかった」
「一度聞いただけでも、だいぶ不安がなくなった」
「家族で話し合うきっかけにしたい」
といった声が寄せられ、大変嬉しく思っております。
次回の講座に向けて
今後も引き続き、公民館や地域施設などで講座を開催していく予定です。
「今回参加できなかったけれど、内容に興味がある」「次回はぜひ聞いてみたい」という方は、当ホームページの「お知らせ」欄をぜひご覧ください。
専門的な内容を、できる限りわかりやすく、日常に役立つ視点でお届けしてまいります。
ご家族・ご友人との参加も大歓迎です。次回の開催をどうぞお楽しみに!